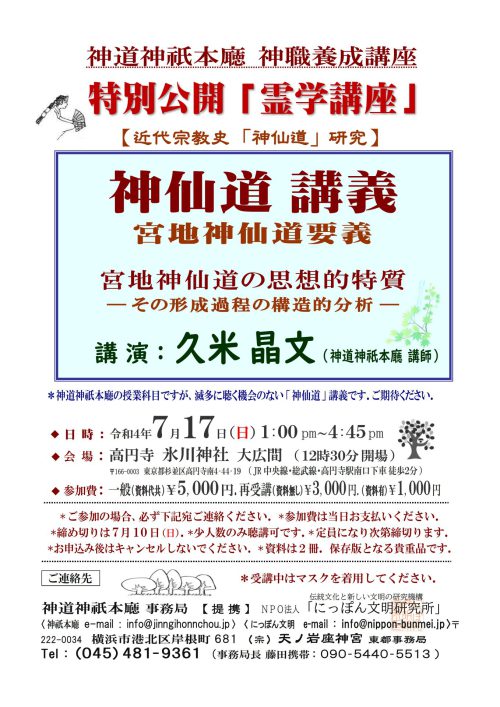トピックス
 -岩笛吹奏と ひと形焼却の神事-
-岩笛吹奏と ひと形焼却の神事-
『 災禍と邪気を祓い社会の繁栄発展と皆さんの弥栄と健康を願う大祓え 』
◎ コロナ禍の影響により変更となりました。
今回は、一般参列を中止し受講生のみにて執り行います。
| 岩笛吹奏 と ひと形焼却の神事 » 事務局までお問合せ下さい | |
| 開催日 : | 令和 4年 6月26日(日) |

令和3年度:水無月大祓祭 について
毎年、6月と12月には國學院大學院友会館で大祓祭を執り行ってきましたが、新型コロナウイルス感染対策の為、院友会館での式典は中止となりました。
今回は、一般参列を中止し受講生のみにて執り行います。
| 受講生の皆様へ |
『 祭式講習会 』は神道神祇本廰に移行しました。神道神祇本廰のサイトからご確認ください。
日本の古い葬儀の様式
神葬祭の推進
葬儀・死生観の違い
諡 と 戒名(法名・法号)
家庭での祀り方
葬儀を行う施設
墓所・墓石
遺族・弔問の作法
祭詞とお経
■ 神葬祭の流れ
■ 古来の「死の文化」に目覚めよ 世界日報掲載記事 (平成22年8月29日)
奈良泰秀 連載コラム 宗教新聞掲載(2003/12 ~ 2008/4)
| 1 | イスラームの生死観 -終末には肉体を持って復活- | 2003/12/5・20合併号 |
| 2 | 伊勢の神宮と遷宮 -清浄さと永遠性の意義を伝える- | 2004/1/20号 |
| 3 | 祭りの創出 -渡来系の影響色濃い神社と新しい祭り- | 2004/2/5号 |
| 4 | 磐座(いわくら)祭祀の意義 -自然と神と ひととの共生- | 2004/2/20号 |
| 5 | 戦没者慰霊と神秘体験 -頭を垂れる英霊の姿- | 2004/3/5・20合併号 |
| 6 | 時代が変える葬送儀礼 -神道葬祭、微増の兆し- | 2004/4/5号 |
| 7 | 古史古伝の世界(上) -判官びいきに通ずる想い- | 2004/4/20号 |
| 8 | 古史古伝の世界(中) -宗教書としてのアピールを- | 2004/5/5号 |
| 9 | 古史古伝の世界(下) -「先代舊事本紀」を再検討- | 2004/5/20号 |
| 10 | 秋田・唐松神社にて -物部の神の復権- | 2004/6/5号 |
| 11 | 神道と古神道 -古神道精神の復権に向けて- | 2004/6/20号 |
| 12 | 宮中三殿 -宮中祭祀神道の意義- | 2004/7/5号 |
| 13 | 華道講座に想う -神籬(ひもろぎ)華道の創設に向けて- | 2004/7/20号 |
| 14 | 夏、フラワー・チルドレンの回想 -師が勧めた戦没者慰霊- | 2004/8/5・20合併号 |
| 15 | 朝鮮神宮のこと -「檀君国師堂」建立に向けて- | 2004/9/5号 |
| 16 | 日本の麻について -麻文化の復権- | 2004/9/20号 |
| 17 | 精神(こころ)と作法(かたち) -手造りの古神道講座- | 2004/10/5号 |
| 18 | 新宗教と埋没神(上) -甦る伊都能売神- | 200/10/20号 |
| 19 | 新宗教と埋没神(中) -古事記に一度出現の伊豆能売- | 2004/11/5号 |
| 20 | 新宗教と埋没神(下) -伊都能売神社の建設を- | 2004/11/20号 |
| 21 | 祓えと大祓え(上) -罪と穢れについて- | 2004/12/5・20合併号 |
| 22 | 祓えと大祓え(中) -穢れと大祓え- | 2005/2/5号 |
| 23 | 祓えと大祓え(下) -再興させたい臨時の大祓え- | 2005/2/20号 |
| 24 | 大祓詞と天津祝詞の太祝詞(上) -混同されている大祓詞- | 2005/3/5号 |
| 25 | 大祓詞と天津祝詞の太祝詞(中) -宣命体と奏上体- | 2005/3/20号 |
| 26 | 大祓詞と天津祝詞の太祝詞(下) -平田篤胤の天津祝詞- | 2005/4/5号 |
| 27 | 大祓詞と天津祝詞の太祝詞(続・1)-伝わらない太祝詞事- | 2005/4/20号 |
| 28 | 大祓詞と天津祝詞の太祝詞(続・2)-行事からみたい太祝詞事- | 2005/5/5号 |
| 29 | 空手道部の合宿 -元伊勢への関心- | 2005/5/20号 |
| 30 | 元伊勢ロマン‥ -「倭姫命世記」の伝承- | 2005/6/5号 |
| 31 | 元伊勢の伝承の源流(1) -伊勢神道と神道五部書- | 2005/6/20号 |
| 32 | 元伊勢の伝承の源流(2) -偽書説と歴史ロマン- | 2005/7/5号 |
| 33 | 元伊勢の伝承の地・奈良(1) -倭姫命世記から派生- | 2005/7/20号 |
| 34 | 元伊勢の伝承の地・奈良(2) -諸説ある笠縫邑- | 2005/8/5・20合併号 |
| 35 | 元伊勢の伝承の地・奈良(3) -信仰心が伝承を土着化- | 2005/9/5号 |
| 36 | 「シオン長老の議定書」の背景 -創られた予言と警告の書- | 2005/9/20号 |
| 37 | 宇宙神教光明会 -元気を取り戻す新宗教- | 2005/10/5号 |
| 38 | 近代神社神道・雑感(上) -神仏習合からの脱皮- | 2005/10/20号 |
| 39 | 近代神社神道・雑感(中) -国学者たちの蠢動- | 2005/11/5号 |
| 40 | 近代神社神道・雑感(下) -大教宣布のゆくえ- | 2005/11/20号 |
| 41 | 国学の巨星・本居宣長(上) -南都・松坂にて- | 2005/12/5・20合併号 |
| 42 | 国学の巨星・本居宣長(中) -少年時代の宣長- | 2006/1/20号 |
| 43 | 国学の巨星・本居宣長(下・一) -もののあわれ- | 2006/2/5号 |
| 44 | 国学の巨星・本居宣長(下・二) -桜好きの宣長- | 2006/2/20号 |
| 45 | 岩 笛 (上) -縄文の岩笛- | 2006/3/5号 |
| 46 | 岩 笛 (下) -神代の楽器・岩笛- | 2006/3/20号 |
| 47 | 清 祓 い (上) -霊能者の師- | 2006/4/5号 |
| 48 | 清 祓 い (中) -競売物件の怪- | 2006/4/20号 |
| 49 | 清 祓 い (下) -『笑翁』異聞- | 2006/5/5号 |
| 50 | ハタミ大統領への手紙 (上) -右傾化するイラン- | 2006/5/20号 |
| 51 | ハタミ大統領への手紙 (下) -宗教間対話の推進を- | 2006/6/5号 |
| 52 | 番外編 五十代からの神道 (1) -アラブへの旅立ち- | 2006/6/20号 |
| 53 | 番外編 五十代からの神道 (2) -イン・シャー・アッラー- | 2006/7/5号 |
| 54 | 番外編 五十代からの神道 (3) -神職養成の見直し- | 2006/7/20号 |
| 55 | 番外編 五十代からの神道 (4) -チュニジアの空手格闘家- | 2006/8/5・20合併号 |
| 56 | 番外編 五十代からの神道 (5) -旅人のゆくえ- | 2006/9/5号 |
| 57 | 番外編 五十代からの神道 (6) -世界に発信する神道を- | 2006/9/20号 |
| 58 | 沖縄縣護國神社 -沖縄戦没者の慰霊- | 2006/10/5号 |
| 59 | 台湾の神社と忠烈祠(上) -総統が祭典の主祭者に- | 2006/10/20号 |
| 60 | 台湾の神社と忠烈祠(下) -大半が能久親王を奉斎- | 2006/11/5号 |
| 61 | 神社の伝承(上) -日本最古の石上神宮- | 2006/11/20号 |
| 62 | 神社の伝承(中) -鎮魂祭の起源- | 2006/12/5号 |
| 63 | 神社の伝承(下) -足踏み・歩行の呪術- | 2006/12/20 号 |
| 64 | 元伊勢原像(一) -廃村に立つ石碑- | 2007/2/5 号 |
| 65 | 元伊勢原像(二) -水銀をめぐる闘い- | 2007/2/20号 |
| 66 | 元伊勢原像(三) -ミステリアスな丹生都比売神- | 2007/3/5号 |
| 67 | 元伊勢原像(四) -『先代舊事本紀』と『倭姫命世記』- | 2007/3/20号 |
| 68 | 元伊勢原像(五) -製鉄史で読み解く神道- | 2007/4/5号 |
| 69 | 元伊勢原像(六) -神宮“創祀二千年”と古代暦- | 2007/4/20号 |
| 70 | 元伊勢原像(七) -元伊勢伝承と壬申の乱- | 2007/5/5号 |
| 71 | 元伊勢原像(八) -見直し進む古代史- | 2007/5/20号 |
| 72 | 元伊勢原像(九) -百数十もの比定地が- | 2007/6/5号 |
| 73 | 元伊勢原像(十) -伝承の起点、笠縫邑- | 2007/6/20号 |
| 74 | 元伊勢原像(十一) -伊豆加志本宮から紀伊へ- | 2007/7/5号 |
| 75 | 元伊勢原像(十二) -紀氏と日前國懸神宮- | 2007/7/20号 |
| 76 | 元伊勢原像(十三) -広い範囲の名方濱宮- | 2006/8/5・20合併号 |
| 77 | 元伊勢原像(十四) -三たび倭への遷幸- | 2007/9/5号 |
| 78 | 元伊勢原像(十五) -御室山に坐す神- | 2007/9/20号 |
| 79 | 元伊勢原像(十六) -樋口清之博士と箸墓古墳- | 2007/10/5号 |
| 80 | 元伊勢原像(十七) -内行花文鏡と製鉄- | 2007/10/20号 |
| 81 | 元伊勢原像(十八) -殉葬の古代史- | 2007/11/5号 |
| 82 | 元伊勢原像(十九) -謎の大物主神- | 2007/11/20号 |
| 83 | 元伊勢原像(二十) -古代への憧憬- | 2007/12/5・20合併号 |
| 84 | 番外編 聖地エルサレム -宗教間対話で中東平和を!- | 2008/2/5 号 |
| 85 | 元伊勢原像(二十一) -三輪から宇陀へ- | 2008/2/20号 |
| 86 | 元伊勢原像(二十二) -伝承をつくる倭姫命- | 2008/3/5号 |
| 87 | 元伊勢原像(二十三) -そして伊勢へ‥‥- | 2008/4/20号 |